静かな退職が園を蝕む危険
「静かな退職(Quiet Quitting)」という現象をご存知でしょうか。社員が表面上は在籍しているものの、熱意や意欲を失い、最低限の業務しかしない状態を指します。エン・ジャパンの調査によると、5社に1社がすでに該当社員を抱え、300人以上の企業では90%以上が「存在する可能性がある」と回答しています。
保育業界にとって最も深刻な問題
この現象を「一般企業の話」として見過ごすことはできません。人が価値そのものである保育業界こそ、最も深刻な影響を受ける分野なのです。
保育現場の「静かな退職」は命に関わります
・子どもの変化に気づかない
・アレルギーや避難対応を怠る
・発達支援が形式的になる
保育は”熱意と気づきの仕事”です。この熱が冷めた職員が無言で現場にいることで、園は気づかぬまま深刻なリスクにさらされます。
組織を蝕む3つのリスク
1.組織の生産性と成長の阻害
新しい提案が出なくなり、「あの人が手を抜いている」と感じた周囲も沈黙します。給与は払っていても成果が伴わない状況が続くのです。
2.人材マネジメントの複雑化
経験豊富な40代職員の「退職しない退職」や、ルーティン業務しかこなさず挑戦しない状態の温存により、組織が硬直化していきます。
3.企業文化の悪化
「言われていないことはしない」空気が蔓延し、「何度言っても変わらない」現象が常態化。人間関係を理由にした実質的な業務放棄も発生します。
保育チーム内に広がる沈黙の連鎖
保育現場では特に深刻な問題が発生します。
・意欲的な保育者に業務が偏る
・「自分ばかりがやっている」と感じて燃え尽きる
・チームの雰囲気が冷え、保護者の信頼も揺らぐ
静かな退職は“辞めない退職”であり、この状態が連鎖すれば、実際の退職者を生む土壌にもなります。
園経営者が取るべき3つの対応策
1.早期発見と予防の仕組み構築
月1回の気持ち面談で変化をキャッチし、業務量の見える化で偏りを防ぎます。キャリアアップ面談制度を導入し、職員の孤立を防止することが重要です。
2.”働きがい”の見える化
専門性の承認と適正な報酬により、年齢一律の給与体系を脱却します。主任や園長への道筋を明確にし、研修・リーダー体験の機会づくりで成長実感を提供します。
3.保育の原点に立ち返る
保育理念を全体で再確認し、「なぜこの仕事をしているのか」を共有します。子どもの変化・成長を共有し、「あなたの関わりで変わったんだ」と伝えることで、保護者からの感謝を現場に届ける工夫が必要です。
心の退職に気づく経営力
私たちは、退職届が出される前に”心の退職“に気づける園でなければなりません。なぜなら、子どもたちは職員の”気持ち”を敏感に感じ取り、その空気は職員同士、保護者にも伝播していくからです。
「静かな退職」とは、働く人の”やる気の声なき喪失”です。園にとっては、見えないまま保育の質をむしばむ沈黙の病とも言えるでしょう。
持続可能な園運営のために
これは経営者として「気づける力」が試されるテーマです。人手不足の時代だからこそ、”辞めない”ではなく、”熱意を持ち続ける”職員をどう育てるか。
この問いに真摯に向き合う経営こそが、これからの園を持続可能にします。職員一人ひとりの熱意が子どもたちの成長を支え、保護者の信頼を築き、園の未来を創造するのです。
静かな退職は見えない危機ですが、適切な対応により防ぐことができます。職員の心の変化に敏感な経営者こそが、真に子どもたちのための保育環境を作り上げることができるのです。
結論 「見えない心の退職に、見える愛で応える」
文責 幼稚園経営コンサルタント 安堂達也

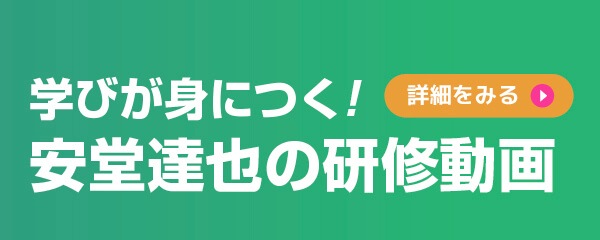
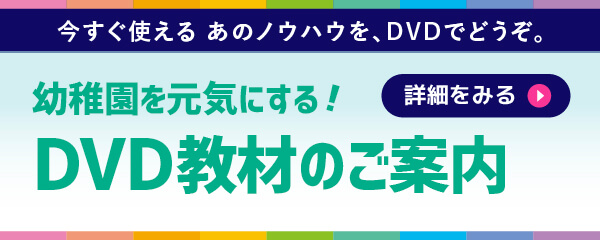

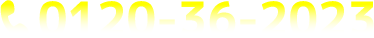 《受付時間》平日9:00〜17:00/土日祝 定休
《受付時間》平日9:00〜17:00/土日祝 定休